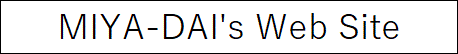岩村城跡〈60枚〉
~ 日本三大山城・標高717m・六段壁

岩村城跡
訪問記念
2021.8
訪問記念
2021.8
作成
▶ 岩村城跡
~ 日本三大山城・標高717m・六段壁
2021年7月、岐阜旅行に行きました。岩村城は恵那市にある山城です。標高717mに位置し、霧ヶ城の別名を持ちます。1185年(文治元年)に源頼朝の重臣加藤景廉がこの地の地頭になると長男景朝が築城し、16世紀中に遠山氏・武田氏により本格的な城山が築かれたとされています。織田信長の五男の御坊丸が遠山氏の養子になると、幼少の養子の代わりに織田信長の叔母が実質的な城主となり差配を振るったとされる「おんな城主おつや」の伝説があります。山裾の藩主邸跡から急な坂道を登ると門跡や石垣があり、頂上部の本丸には六段壁という六段の石垣があります。高取城、備中松山城と共に日本三大山城の1つに数えられ、日本100名城に選定されています。
……………… スポット情報 ………………
エリア 中部地方  岐阜県
岐阜県
所在地 岐阜県恵那市岩村町城山 [MAP]
アクセス明知鉄道「岩村」駅徒歩25分で登山口
関連HP女城主の里いわむら【公式】戦国の世を凛として生きた、おんな女城主おつや | 恵那市観光協会が運営する「おんな城主」公式観光情報サイト。
※画像の無断利用を禁じます 写真の利用と禁止事項
*Use of images is prohibited. Details