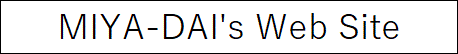丸亀城〈60枚〉
~ 高石垣の名城・現存12天守の1つ

丸亀城
訪問記念
2021.10
訪問記念
2021.10
作成
▶ 丸亀城
~ 高石垣の名城・現存12天守の1つ
2021年10月、香川旅行に行きました。丸亀城は丸亀市にある平山城で亀山城、蓬莱城ともいいます。丸亀城は生駒親正により高松城の支城として慶長2年(1597年)に築城開始され、1615年(元和1年)に一国一城令で一旦廃城となりました。後に丸亀藩を立藩した山崎氏に変わり京極高和により城の大改修が行われ、1660年(万治3)に現存する天守が完成しています。
石の城として知られ、一二三段といわれる四重の高石垣は総高60mで日本一の高さを誇ります。頂に向かって角度が増して垂直になる高石垣は「扇の勾配」とも呼ばれています。天守、大手一の門、大手二の門は国の重要文化財に指定されています。現存十二天守の1つであり、日本100名城に選定されています。
……………… スポット情報 ………………
エリア 四国地方  香川県
香川県
所在地 香川県丸亀市一番丁 [MAP]
アクセスJR予讃線「丸亀」駅徒歩10分
関連HP丸亀城(日本100名城・現存十二天守) - 香川県丸亀市にある石垣の名城
※画像の無断利用を禁じます 写真の利用と禁止事項
*Use of images is prohibited. Details