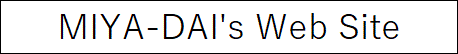足尾銅山(坑内観光)〈80枚〉
~ 日本一の銅山跡・トロッコで入坑

足尾銅山
訪問記念
2024.4
訪問記念
2024.4
作成
▶ 足尾銅山(坑内観光)
~ 日本一の銅山跡・トロッコで入坑
2024年4月、足尾と宇都宮へ旅行に行きました。足尾銅山観光は足尾銅山の坑内を利用した観光施設です。足尾銅山は1610年(慶長15年)に採掘が始まり、明治時代には日本一の銅生産量を誇り、1973年(昭和48年)に閉山しています。総延長は1,234kmに達しています。
現在の観光施設はトロッコ電車に乗って坑内に入り、そこから徒歩で坑内を歩きます。薄暗い坑道の様子や採掘の様子が人形などで再現され、時代ごとのエリア(江戸、明治・大正、昭和)に分かれて技術の変化を感じることができます。奥には鉱石や製錬等を展示する銅(あかがね)資料館があります。
……………… スポット情報 ………………
エリア 関東地方  栃木県
栃木県
所在地 栃木県日光市足尾町通洞9-2 [MAP]
アクセスわたらせ渓谷鐵道「通洞」駅徒歩5分
関連HP足尾銅山観光|体験・観光スポット |【公式】日光市の観光サイト 日光旅ナビ
※画像の無断利用を禁じます 写真の利用と禁止事項
*Use of images is prohibited. Details